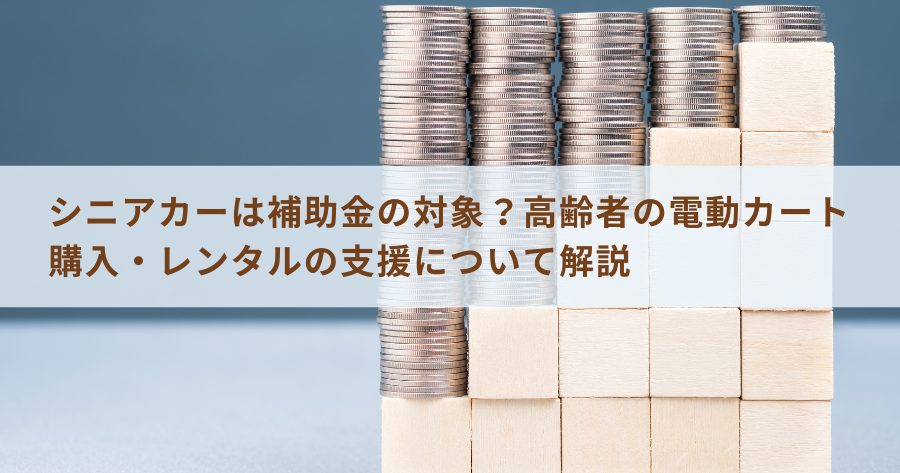電動車いすでの外出を快適に!福祉車両の種類と選び方・注意点を解説
- 2025.07.07
最終更新日 2025.7.7.
電動車いすでの外出は「車の乗り降りが不安」「段差や介助の負担が大きい」と、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。移動の不安から、外出を諦めてしまうケースも少なくありません。
そのようなときに頼りになるのが、電動車いすに対応した福祉車両です。福祉車両を活用すれば、移動がラクになり、行動の幅も広がります。
この記事では福祉車両の種類や特徴、必要な免許や注意点などを解説します。安心して外出を楽しみたい方は、ぜひ参考にしてください。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
電動車いすでの外出をサポートする福祉車両とは

ここでは、福祉車両の定義と一般車との違いを解説します。
福祉車両の定義
福祉車両とは、高齢者や身体が不自由な方、介助する方が安心かつ快適に移動できるよう特別な工夫が施された車のことです。
福祉車両は単なる移動手段ではありません。利用者の通院や買い物など日常生活での外出を支え、生活の質(Quality of Life)を高める大切な役割を担っています。
一般車との違い
福祉車両と一般車には、利用者の乗り降りや安全を守るために大きく分けて以下の3つの違いがあります。
| 違い | 機能・装備 | メリット |
|---|---|---|
| ①乗り降りのしやすさ | ・スロープ/リフト ・回転/昇降シート | 車いすのまま乗車でき、介助者・利用者の身体的負担が軽減される |
| ②移動中の安全性 | ・車いす固定装置 ・手すり/補助バー | 走行中の揺れや衝撃から体を守り、安心してドライブを楽しめる |
| ③多様なサポート | ・運転補助装置 ・各種優遇措置(非課税、助成金) (※制度の内容は地域や条件によって異なります) | 身体状況に合わせた運転が可能になり、購入・維持の経済的負担も軽くなる |
福祉車両には一般車にはない工夫や配慮があり、外出をより快適で安心なものにしてくれます。
電動車いす対応の福祉車両を選ぶポイント

ここでは、使用目的と乗降スタイルの2つの視点から福祉車両の選び方のポイントをご紹介します。
使用目的で選ぶ
福祉車両を選ぶ際は、誰が運転しどのように乗るのかという使用目的を明確にしましょう。使用目的が以下の表のどちらに当てはまるかによって、選ぶべき福祉車両のタイプが異なります。
| 使用目的 | 車両タイプ | 特徴 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|
| 介助者が運転し、利用者は車いすのまま乗車 | 介護車(車いす乗車専用) | ・車いすのまま乗降・固定が可能 ・安全に固定する器具を完備 ・乗り降りの負担が少ない | ・車いすに座ったまま移動したい方 ・介助者と一緒にお出かけする方 |
| 利用者が補助装置を使って運転 | 自操車(運転補助装置付き車両) | ・手動レバーなど運転補助装置を装備 ・利用者の身体状況に合わせて改造 | 手足に障害があっても自分で運転したい方 |
利用する方の身体の状態や生活スタイル、介助の有無に合ったタイプを選ぶと、無理なく安心して移動ができます。
乗降スタイルで選ぶ
介護車には乗り降りの方法によって複数のタイプがあり、それぞれに特徴があります。利用する方の状態に合わせてタイプを選ぶと、乗り降りがしやすくなり、介助の負担も軽減されます。
| タイプ | 特徴 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| スロープ式 | ・車の後方や横に板状のスロープをかけて、車いすのまま乗車 ・スロープは手動または電動式 | 軽い電動車いすや手動車いすを使う方 |
| リフト式 | ・電動リフトで車いすごと持ち上げて乗車 ・ボタン一つで操作可能 | 重い電動車いすを使う方 |
| 回転シート式 | ・助手席や後部座席が外側に回転し、スライドして乗車 ・座ったまま車内へ移動可能 | 歩行は可能だが足腰が弱く、車の乗り降りに不安がある方 |
電動車いすには、軽いものから重いものまで、さまざまなタイプがあります。特に重量のあるタイプを使う場合は、車両のサイズや固定方法が適しているか、あらかじめ確認しておきましょう。
電動車いす対応の福祉車両を利用する際の注意点

ここでは、電動車いす対応の福祉車両を利用する際の注意点をご紹介します。
①一部の福祉車両では中型・大型免許が必要になる場合がある
電動車いすに対応した福祉車両の多くは、普通自動車免許で運転が可能です。ただし、すべての車両に当てはまるわけではありません。
例えば、乗車定員が11人以上の車両や、福祉施設で使われるバス仕様の送迎車などは、中型免許または大型免許が必要です。車両サイズや構造によっては、普通免許では対応できないケースがあるため注意が必要です。
また、運転補助装置を備えた自操車は、普通免許で運転できる場合がほとんどですが、身体の状態に応じて「手動装置付き車両に限る」などの条件が免許証に記載される場合もあります。
購入やレンタルの前に、車両の仕様書や免許の条件欄を確認しておくと安心です。
②有償送迎を行う場合は第二種免許が求められる場合がある
送迎の目的やサービスの内容によって、必要な免許は異なります。以下の一覧で、用途ごとの違いを確認しましょう。
| 用途・運用形態 | 第一種免許 | 第二種免許 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| 無償送迎(自家用、施設の送迎サービスなど) | 〇 | ー | 家族の送迎や施設が運賃を受け取らずにサービスの一環として送迎する場合 |
| 福祉有償運送(NPO法人などによる非営利の送迎) | 〇(※注1) | 〇 | 【第一種免許で運転する場合の条件】 ・NPO法人などが運輸支局に登録 ・運転者が福祉有償運送運転者講習を修了 |
| 介護タクシー(事業として運賃をもらう送迎) | ✖ | 〇 | 営利目的の旅客運送事業のため、必ず第二種免許が必要 |
| 運転補助装置を使用 | 〇(※注2) | ー | 身体条件に応じた免許条件付与 |
(※注1)福祉有償運送を行うには、団体の登録と運転者が福祉有償運送運転者講習を修了することが必須です。
(※注2)運転する車両は普通自動車(マイクロバスを除く)を想定しています。
送迎の形態により必要な免許は異なるため、事前に地域の運輸支局や自治体に確認しましょう。
参考:道路運送法第七十八条二項|e-GOV法令検索
福祉有償運送ガイドブック|国土交通省
③一般車に比べて費用が高く、選択肢が限られる場合がある
福祉車両は搭載する装備によって、一般車より購入価格や維持費用が高くなる傾向にあり、車種や仕様の選択肢も限られます。
例えば、同じ車種でも一般車と福祉車両では、10万円以上価格が異なります。これは、電動車いすが乗り降りするためのスロープやエアサスペンション、電動ウインチなどの装置が搭載されているためです。
これらの装備は安全性確保のための定期点検が欠かせないため、維持費も一般車と比較して年間で5,000〜1万5,000円高くなります。(※部品の交換が必要な場合は別途工賃が発生、費用は業者によって異なる)
また、各自動車メーカーが提供している福祉車両のラインナップは、主に以下の3つのカテゴリーに集中しています。
| 車両タイプ | 特徴 | 代表的な車種 |
|---|---|---|
| ミニバン | スロープタイプやリフトタイプが豊富にある | ・トヨタ:シエンタ/ノア/ヴォクシー ・日産:セレナ/ノートなど |
| コンパクトカー | 助手席が回転・昇降するタイプが多く見られる | ・トヨタ:ルーミー/アクア ・スズキ:ソリオなど |
| 軽自動車 | 電動車いす仕様車からシート昇降タイプまでさまざまなモデルがある | ・ホンダ:N-BOX/フィット ・ダイハツ:タント ・スズキ:スペーシア/エブリイなど |
スポーツカーやセダン、一部のSUVなどは、乗降口の狭さ・車高の低さ・車内空間などの要因により、福祉車両への改造が難しいため、メーカー純正の福祉車両として提供されることはほとんどありません。
多くの福祉車両には搭載できる電動車いすのサイズや重量に制限があり、特に高機能な電動車いすのなかには、制限を超えるモデルが存在するため、電動車いすを自動車ディーラーに持ち込み、実際に乗せ降ろしすることが重要です。
電動車いす福祉車両で広がる外出のメリット

ここでは、電動車いす福祉車両を使った外出で得られる5つのメリットをご紹介します。
①病院への移動負担が軽減される
病院への通院は、福祉車両を利用すれば移動の負担を軽減できます。車いすのまま乗車できるため、車いすから座席に乗り換える必要はありません。
雨の日でも濡れずに済み、定期的な受診がしやすくなるだけでなく、体調が急変した際も柔軟に対応でき、家族や介助者の負担も軽減できます。
②気軽にレジャーやドライブが楽しめる
福祉車両を使えば、安心してレジャーやドライブを楽しめます。乗り降りをスムーズにするための手すりや段差の自動調整機能、車いすをしっかり固定するベルト、専用のシートベルトなど、安全装置が充実しているためです。
③家族や友人と外出する機会が増える
福祉車両を利用すれば移動の負担が軽くなり、外出のハードルも下がります。移動時の不安や身体への負担が減るため、気軽に出かけようという気持ちが芽生えてきます。
こうした気持ちの変化が、家族や友人とのお出かけの機会を自然と増やしてくれるでしょう。
④公共交通機関では不便な場所にもアクセスできる
福祉車両を活用すれば、公共交通機関では行きづらい場所にも快適に移動できます。乗り換えの手間や混雑のストレスがなく、自宅から目的地までスムーズに移動できるためです。
⑤自分のペースで自由に外出できる
福祉車両を利用すれば、自分のペースで無理なく外出を楽しめます。体調や予定に合わせて出発や休憩のタイミングを調整できるため、周囲に気を使う必要がありません。
車いすを利用する方も、介助する家族の方もゆったりと過ごせるので、リラックスしながら外出を満喫できます。
電動車いすの外出には「モ二スタ」があると安心

離れて暮らすご家族はもちろん、電動車いすを利用するご本人にとっても、1人での外出には不安があるでしょう。そのような外出時の見守りに役立つのが、GPS機能を搭載した電動車いす用モニタリングシステム「モニスタ」です。
スマートフォンやパソコンから、位置情報や走行状況をリアルタイムで確認・共有できるため、万が一のトラブルや体調の変化にもすばやく対応可能です。
また、バッテリー残量やタイヤの交換時期も把握でき、日々のメンテナンスにも役立ちます。外出時の不安を軽減し、安全な移動をサポートします。大切なご家族の安心のために、ぜひ導入をご検討ください。
まとめ:福祉車両を活用して、電動車いすの外出をもっと快適に

電動車いすでの外出には、福祉車両を取り入れると移動がスムーズになり、介助する側の負担も軽減されます。利用者の状況に応じた車両を選べば、自分のペースで安心して外出でき、行動の幅も広がるでしょう。
さらに、GPS機能付きの見守りサービス「モニスタ」を活用すれば、1人での外出や離れて暮らすご家族の見守りにもつながり、安心感が高まります。安全で快適なお出かけのために、ぜひ導入をご検討ください。