離れて暮らす親の不安を解消!同居のメリット・注意点を徹底解説
- 2025.10.27
最終更新日 2025.10.27.
親と離れて暮らす家族にとって「急な体調の変化に気づけない」「困っていてもすぐに駆けつけられない」といった状況は大きな不安です。
特に高齢の親がいる場合、わずかな体調の変化の見逃しも大きなリスクとなるため、心配が尽きません。安心して暮らすために、親との同居を考える方もいますが、事情によっては難しいケースもあります。
この記事では、同居のメリットや注意点、同居が難しい場合に利用できるサポートについて解説します。ぜひ参考にしてください。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
親と離れて暮らす家族の現状と不安

まずは、離れて暮らす家族の現状と不安を解説します。
親と別々に暮らす理由
社会の変化に伴い、親と子が別々に暮らす家庭が増えています。内閣府「高齢社会白書」によると、1980年には高齢者の約7割が子どもと同居していましたが、現在は約4割にまで減少し、一人暮らしや夫婦のみの世帯が目立つようになりました。
厚生労働省「国民生活基礎調査」(2024年)でも同様の傾向が見られ、65歳以上で子どもと同居している方は33.1%にとどまっています。多くの高齢者が、夫婦のみまたは単身で生活しているのが現状です。
※参考:内閣府「高齢社会白書」
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
このような背景には、次の要因が挙げられます。
・核家族化の進行
・都市部への人口集中
・子ども世代の就職や結婚による独立
社会の変化に合わせて、高齢者が安心して暮らせる環境づくりは、多くの家族にとって大きな課題といえるでしょう。
離れて暮らす親への不安
離れて暮らしていると、日ごろ連絡を取っていても生活や体調の細かな変化に気がつかない場合があります。何かあったときにすぐ駆けつけられないのも、大きな不安の一つです。
こうした不安を軽減するために、同居を考える家庭も少なくありません。ただし、同居を決める際は、まず親の意思を尊重し、家族でしっかり話し合う必要があります。
一方で、同居が難しい場合でも、介護サービスや見守りサービスを活用すれば、離れていても安心できる体制を整えられます。
離れて暮らす親と同居を考えるタイミング

同居を検討するきっかけは状況によって異なりますが、親の体調や生活の変化を機に考え始めるケースが多くみられます。
| 同居を考えるきっかけ | 具体的な出来事 |
|---|---|
| 健康状態の変化 | ・認知症の兆候がみられる ・転倒や入院をした ・持病が悪化した |
| 生活面の不安 | ・火の扱いに不安がある ・金銭管理が難しい ・防犯面に心配がある |
| 介護の必要性 | ・要介護認定を受けた ・介護サービスが足りない ・施設入居を希望しない |
| 家族のライフステージの変化 | ・子どもが独立した ・配偶者を亡くした |
| 遠距離介護の限界 | ・頻繁な帰省で負担が増えた ・緊急時に対応できない ・精神的・体力的な負担が大きい |
こうした変化や状況に応じて、見守りサービスや介護の支援を取り入れ、無理なく同居を検討できるよう家族で話し合っておきましょう。
離れて暮らす親との同居を判断する際のポイント

ここでは、同居を判断する際に意識しておきたいポイントをご紹介します。
①親の意思を尊重できるか
同居を考える際は、まず親の意思を尊重しましょう。「迷惑をかけたくない」「自分のペースで暮らしたい」と思う親も、少なくありません。
本人の希望を無視して同居を進めると、不満やストレスが生じ、親子関係が悪化するおそれがあります。親の意思を聞き取り、家族間で共有しておきましょう。
②同居後の生活設計が描けるか
事前に生活ルールや役割分担などを話し合い、具体的な生活設計を立てておくことも重要です。同居を始めると、生活習慣や価値観の違いから家族間のトラブルにつながるケースがあるからです。
例えば、家事の分担や生活費の負担を明確にしないままだと、お互いに不満が募り、家族関係がぎくしゃくする原因になります。同居後の生活設計は、同居前にイメージしておきましょう。
③制度や地域のサービスを活用できるか
同居後の親の介護に備えて、利用できる制度やサービスは事前に調べておきましょう。そうすれば、いざというときに慌てず、最適なサポートを受けられます。
例えば、デイサービスや訪問介護を利用すれば家族の負担を軽減できます。地域包括支援センターでは、状況に応じて介護サービスや地域の支援につないでもらえます。利用できる制度やサービスは地域によって異なるため、まずは相談してみましょう。
離れて暮らす親と同居するメリット

ここでは、離れて暮らす親と同居するメリットをご紹介します。
親の体調の変化に早期に気づける
同居していれば、親の顔色や食欲、歩き方など、日常のちょっとした変化にも気づきやすくなります。また、物忘れの増加や外出の機会の減少にも、早めに気づけるでしょう。
こうした変化を早い段階で把握できれば、病院の受診や介護サービスの利用につなげやすくなり、家族も安心して見守ることができます。
日常の助け合いで家族の絆が深まる
同居していると、買い物や食事の準備、掃除など、日常の家事を家族で分担できるのも大きなメリットです。親が元気なうちは、家事を手伝ってもらえるため、子世帯の負担を減らせます。
日々の交流や食卓を囲んで会話を楽しむ時間が増えれば、孤独感をやわらげ家族の絆もいっそう深まるでしょう。
光熱費や住居費を共有して生活費を節約できる
親と同居すれば、世帯全体の生活費を節約できます。これまで二世帯でそれぞれ支払っていた光熱費や住居費を一本化したり、食材や日用品などもまとめて購入したりすれば、コストダウンになります。
また、親が賃貸で暮らしている場合は、同居によってその分の家賃負担がなくなるため、毎月の支出も大幅に削減できるでしょう。生活費を節約できれば家計にゆとりが生まれ、貯蓄や将来への備えにできます。
離れて暮らす親と同居するデメリット
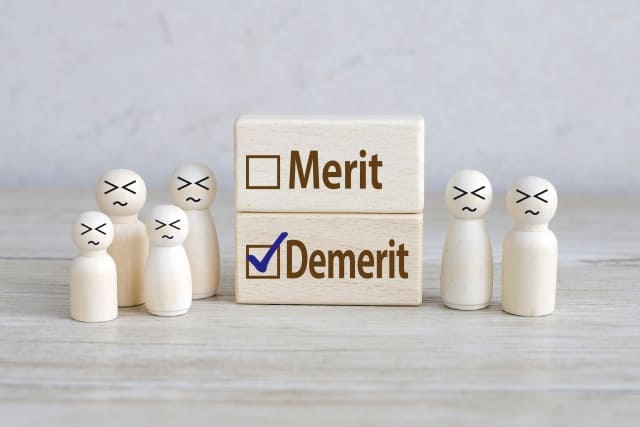
ここでは、離れて暮らす親と同居する主なデメリットをご紹介します。
生活習慣や価値観の違いがストレスになる
同居を始めると、生活リズムや金銭感覚の違いからストレスを感じやすくなります。自分の時間や空間を確保しにくいことがストレスの原因となる場合は、個室や専用スペースを用意しておくと安心です。
また、家事や生活費の負担をめぐり、意見が合わない場合もあるため、事前に家族でルールを決めておきましょう。
慣れない環境にとまどうことがある
高齢の親が子どものもとで同居する場合は、住み慣れた環境を離れる不安や、新しい通院先を探す負担を感じやすくなります。一方、子どもが親のもとに戻る場合は、通勤時間の増加や生活リズムの変化が負担になる場合もあります。
どちらの場合も地域の病院を調べたり、職場まで無理なく通勤できるか確認したりしておくと安心です。
経済的な負担が大きくなる可能性がある
高齢の親が安心して暮らせるよう住まいを整える際には、手すりの設置や段差の解消など、予想以上に費用がかかる場合があります。また、介護が始まると福祉用具や医療費など、出費が増える可能性もあります。
経済的な負担を抑えるためには、介護保険による住宅改修制度や自治体の補助金制度を事前に調べて活用することが大切です。
離れて暮らす親との同居が難しいときに活用できるサポート

ここでは、離れて暮らす親との同居が難しい場合に活用できる支援やサービスをご紹介します。
地域の介護サービス
介護サービスには、介護保険の対象となるものと民間サービスがあり、生活環境に合わせて利用できます。
| サービス | 内容・メリット |
|---|---|
| デイサービス | ・日中に専門スタッフの見守りや機能訓練を受けられる ・家族の介護負担を軽減できる |
| 訪問介護 | ・自宅で生活を続けながら必要な介助を受けられる ・身体介護や生活援助など、柔軟に対応できる |
| 配食サービス | ・栄養バランスの取れた食事を定期的に届けてもらえる ・調理や買い物の負担を減らせる ・配達時に安否確認もできる |
これらを組み合わせれば、見守りや安否確認もでき、離れて暮らしていても安心して過ごせます。利用できる内容は地域で異なるため、自治体に確認してみましょう。
サービス付き高齢者住宅
サービス付き高齢者住宅とは、見守りや生活支援のサービスが付いた高齢者向け賃貸住宅です。バリアフリー設計の住まいには、日中スタッフが常駐し、入居者を見守りながら日々の生活をサポートします。
| 主なサービス | 特徴 |
|---|---|
| 安否確認 | 毎日の様子を確認してくれるため、体調の変化にも早めに気づける |
| 生活相談 | 健康や食事、生活全般に関する相談ができる |
| 夜間対応 | 施設によっては夜間もスタッフが常駐し、緊急時にも対応できる |
同居にこだわらず、親が安心して暮らせる住まいとして利用を検討してみましょう。
あわせて読みたい記事:「サービス付き高齢者住宅のサポート内容とは?メリットや注意点も解説」
ICTを活用した見守りツール
ICT(情報通信技術)を活用した見守りツールは、比較的費用を抑えながら、離れていても家族の様子を確認できます。
| 主なツール | メリット |
|---|---|
| 見守りカメラ | 映像で安否確認ができ、異常があればすぐに気づける |
| 冷蔵庫センサー・通信機能付きポット | 使用状況から安否の確認ができ、特別な操作がいらないため高齢者でも使いやすい |
| モニスタ(電動車いす搭載ツール) | GPSを使って現在の走行位置や移動履歴を専用ページで確認でき、電動車いすでの外出を見守れる |
こうしたツールはプライバシーに配慮しつつ、無理なく見守れるため、安心して取り入れられます。
モニスタ搭載の電動車いすで外出を安心サポート

離れて暮らしていても、親の外出を安心して見守りたい。そのような思いに応えるのが、GPSを搭載した電動車いす用モニタリングシステム「モニスタ」です。
スマートフォンやパソコンの専用ページから、移動履歴や走行状況を確認でき、外出中の様子を見守れます。また、週・月・6か月単位の走行距離や時間など、使用頻度や過去のデータから、外出の変化にも気づけるため、離れて暮らす家族にも安心です。
まとめ:離れて暮らす親に安心を届けよう

離れて暮らす親との同居には、体調や生活の変化に気づきやすいといったメリットがある一方で、注意しておきたい点もあります。同居が難しい場合は、サービス付き高齢者住宅や見守りサービスの利用も一つの方法です。
さらに、「モニスタ」を搭載した電動車いすをプレゼントするのもおすすめです。スマートフォンやパソコンで移動履歴や走行状況を確認できるため、離れて暮らす親の外出状況を把握できます。ぜひ、導入をご検討ください。




