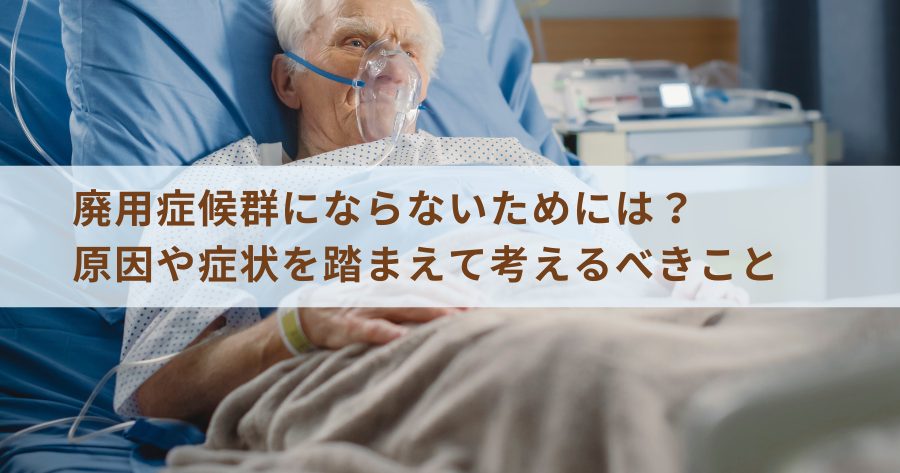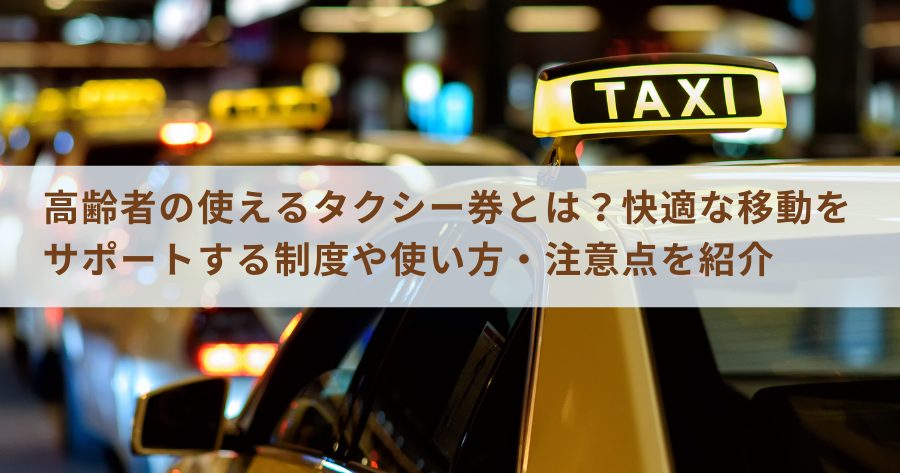介護トラブルはICTで防ぐ!原因と家族でできる予防法を徹底解説
- 2025.08.01
最終更新日 2025.8.1.
家族との意見の対立や、施設での思わぬ事故、そして介護による心身の負担。こうした介護トラブルは、ICT(情報通信技術)を取り入れればリスクを減らせます。
この記事では、介護トラブルの事例や対策、ICTを活かした予防策などを解説します。介護の新常識を味方に、家族の安心と未来を守りたい方は、ぜひ参考にしてください。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
【事例別】介護でよくあるトラブルの種類

ここでは、家族や親族間、現場でよくあるトラブルの事例を取り上げ、経緯を見ていきます。
家族・親族間で起こるトラブル
介護をきっかけに、家族や親族の間でトラブルが起きるケースがあります。ここでは主な事例を3つご紹介します。
①介護の負担が特定の家族に集中する
家族・親族間で起こるトラブルとして多いのが以下です。
| 事例①なぜ私だけ?協力が得られずひとりで介護を負担 |
|---|
| 母の介護が必要になったが、実家の近くに住んでいたのは自分だけ。兄と妹は遠方に住んでいて連絡もほとんどない。気づけば、介護をすべて自分が抱えていた。介護の負担は日ごとに増し、心身ともに限界に追い込まれる。家族に現状を伝えても支援は得られないまま、現在もひとりで介護を続けている。 |
こうした状況が長く続くと、精神的な負担から介護うつを発症するリスクも高まります。その結果、介護の継続が難しくなるケースも少なくありません。
②介護方針を巡って家族間で対立する
以下のように、介護方針を巡り家族間で意見が食い違い関係性が悪くなる場合もあります。
| 事例②施設に入れるべき?介護方針をめぐって兄弟が対立 |
|---|
| 母の認知症が進行し、安全面や介護負担を考えて早めの施設入所を提案する。しかし、妹は自宅で最期まで看たいと主張し、話し合いは平行線のまま。何度も話し合いを重ねたが、状況は変わらなかった。母は自宅での生活を続けることになり、その結果、兄妹間の関係も悪化した。 |
介護方針を巡り対立が続くと、家族の関係に深刻な亀裂が生じます。感情のすれ違いが積み重なり、関係の修復が難しくなる可能性もあります。
③介護費用や金銭管理でもめる
以下のように、介護費用を誰が負担するのか問題でもめるケースも少なくありません。
| 事例③親の介護費用、誰が出す?姉妹の対立に発展 |
|---|
| 父の認知症が進み、母ひとりで介護を続けるのが難しくなっていたため、施設への入居を検討することに。初期費用は父の退職金で、月額費用は年金でまかなえると家族は考えていた。しかし、在宅で暮らす母の生活費も必要となり、その負担をめぐって姉妹の間で意見が対立。深刻なトラブルへと発展した。 |
こうしたトラブルを防ぐには、あらかじめ介護にかかる費用を把握し家族や親族間で話し合うことが大切です。介護費用については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい記事:「親の介護を始める前に知っておくべき費用・ポイント・注意点を徹底解説」
介護現場で起こるトラブル
高齢者の介護には予期せぬトラブルがつきものです。ここでは、介護の現場でよく見られる事例をご紹介します。
①転倒・転落する
以下は、介護の現場でありがちな転倒・転落トラブルです。
| 事例①車いすから椅子への移乗時に転倒 |
|---|
| 施設の食堂で、車いすを利用していたAさんが椅子に移ろうとした際、スタッフが椅子を引いたタイミングと合わずに転倒。左足を骨折した。 |
| 事例②浴室内で転倒し、後頭部を打撲 |
|---|
| 訪問入浴を利用していたBさんが、入浴介助中に椅子ごと後方に転倒し、後頭部を打撲。久しぶりの入浴で筋力が低下していたうえ、介助スタッフは1名のみ。安全確認も十分でなかった。 |
転倒や転落は、骨折などの大きなけがにつながるおそれがあるため、安全確認が大切です。
②食べ物を喉につまらせる
食事中のトラブルも介護現場でよく見られます。
| 事例③しゃっくり中に食事を続け、誤嚥により心肺停止 |
|---|
| 食事介助中にしゃっくりが出たCさんは、そのまま食事を続け、全体の6割ほどを食べたところで終了。その後、苦しそうにしている様子を別のスタッフが発見し、看護師が応急処置を行った。Cさんは一時的に心肺停止の状態となったが、搬送先の病院で意識を取り戻した。 |
食事中の誤嚥や窒息は、命に関わる重大な事故につながる恐れがあります。状態をよく観察し、慎重に対応することが大切です。
③飲む薬や時間を間違える
介護現場では、以下のように高齢者の健康に関わるトラブルが起こる場合もあります。
| 事例④薬袋の日付を確認せずに服薬ミス |
|---|
| 食後、介護スタッフがDさんに薬を手渡した際、名前の読み上げは行っていたが、薬袋の日付を確認していなかった。その後、別のスタッフが確認したところ、前日分の薬が渡されていたことが判明。幸い内容は当日分と同じだったため、健康被害はなかった。 |
複数の薬を服用している高齢者は、薬の取り違いや飲み忘れにより体調を崩す恐れがあります。服薬管理では、ダブルチェックをはじめとする徹底した確認作業が欠かせません。
介護トラブルの主な原因と予防対策

ここでは、在宅介護におけるさまざまなトラブルの主な原因と予防対策を解説します。
①情報共有の不足
家族や介護スタッフとの情報共有がうまくいかないと、認識のズレや対応の食い違いが生じ、トラブルにつながる可能性があります。
| 主な原因 | 予防策 |
|---|---|
| 家族間で介護方針の認識が一致していない | 家族全員で話し合い、役割分担や方針を明確にする |
| 口頭の伝達だけで、記録が残っていない | 共有ノートやグループLINEなど、記録として残るツールを活用する |
| 施設やケアマネジャーとの連携が不十分 | 定期的な面談や連絡帳を通して、こまめに状況を確認する |
日頃から「報告・連絡・相談」を徹底すれば、コミュニケーションが円滑になり、トラブルを未然に防げます。
②不安やプライドの無理解
介護される本人の気持ちやプライドが十分に理解されないと、介護拒否など、支援が難しくなる場合もあります。
| 主な原因 | 予防策 |
|---|---|
| 入浴や排せつの介助に抵抗がある | プライバシーに配慮した介助を心がける |
| プライドが高く、できるだけ人に頼りたくない | 本人の意志を尊重し、できることは任せ、対等な立場で協力する |
| 介護そのものに対して不安や恐怖を感じてしまう | これから行うことをていねいに伝え、本人のペースに合わせて対応する |
本人の意思や気持ちに寄り添った対応を心がけると、信頼関係が生まれ、安心して介護できる環境が整います。
③心身の疲弊
日頃から介護をする家族には、心身への大きな負担がかかります。放置すれば、介護うつや虐待など深刻な問題につながるおそれもあります。
| 主な原因 | 予防策 |
|---|---|
| 排せつや入浴介助など、身体への負担が大きい | デイサービスや訪問介護を定期的に利用して負担を分散する |
| 相談できる相手が身近にいない | 地域包括支援センターに相談し、公的支援制度を早めに活用する |
| 長期間の介護でストレスがたまり、精神的に不安定になる | ショートステイなどを利用し、一時的に介護から離れて心身を休める |
家族に介護が必要になってから慌てないよう、事前に情報を集め、相談できる窓口を確認しておきましょう。
介護トラブルを防ぐICT・デジタル技術の活用法

ICTは情報を効率的に伝達・処理する技術であり、介護の現場でも活用が進んでいます。ここでは、そのなかでも身近で取り入れやすいツールをいくつかご紹介します。
①見守りセンサーやカメラで24時間の安心を確保する
見守りセンサーやカメラを活用すれば、家族がそばにいない夜間や外出中でも室内の様子を把握できるため安心です。
| 以下のような方におすすめ |
|---|
| ・夜間の転倒が心配な方 ・日中仕事で付き添えない方 ・遠方に住む高齢の親を見守りたい方 |
赤外線タイプやマットタイプの人感センサーは、起き上がりや離床を感知し、自動で家族に通知します。見守りカメラを設置すれば、スマートフォンからリアルタイムで様子を確認でき、体調や行動の変化にもいち早く対応できます。
②GPSで外出時の事故リスクを低減する
ひとりでの外出や認知症による徘徊は、家族にとって大きな不安の一つです。外出中の事故リスクを減らすには、GPSの活用が効果的です。
| 以下のような方におすすめ |
|---|
| ・徘徊の恐れがある高齢者を介護している方 ・ひとりでの外出中の安否確認をしたい方 ・離れて暮らす家族を見守りたい方 |
小型のGPS端末を携帯すれば、スマートフォンで居場所を確認でき、緊急時にも対応できます。靴に装着できるタイプもあり、端末の持ち歩きが難しい方でも無理なく使えます。
③服薬アプリで飲み忘れを回避する
高齢者は服薬の管理が難しくなり、飲み忘れや誤飲のリスクも高まります。対策として有効なのが、服薬をサポートするアプリです。
| 以下のような方におすすめ |
|---|
| ・薬の飲み忘れが増えてきた高齢の親がいる方 ・服薬状況を家族で把握しておきたい方 ・服薬ミスによる健康トラブルを防ぎたい方 |
服薬アプリは、服薬時間を音や通知で知らせるほか、服用状況の記録や確認も可能です。家族と情報を共有しておけば、飲み忘れの早期発見や日常的な見守りにもつながります。
④情報共有ツールで家族の連携を強化する
在宅介護では、離れて暮らす家族や介護に関わるスタッフとの情報共有が欠かせません。Zoomなどのオンラインツールを活用すれば、介護方針や状況をリアルタイムで共有でき、伝達ミスを防げます。
| 以下のような方におすすめ |
|---|
| ・家族で介護を分担している方 ・情報共有がうまくいかず困った経験がある方 ・離れて暮らす親の介護をしている方 |
情報共有ツールなら、サービス担当者会議や退院時カンファレンスも遠隔で行えるため、移動の負担を減らしながらスムーズな連携が可能です。
「今日の外出」がスマホでわかるモニスタ。電動車いすの見守りで介護トラブルの不安を安心へ

在宅介護における心配ごとの一つが、家族がひとりで外出されるとき。「もし、道に迷ったら」「何かあったら……」そのような電動車いすでの外出時の不安に寄り添い、安心を届けるのがGPS見守りサービス「モニスタ」です。
スマートフォンやパソコンから、走行ルートや活動時間といった日々の使用状況を確認できるため、離れて暮らす家族も穏やかな気持ちで見守れます。さらに、バッテリーやタイヤなどの交換時期も通知されるため、メンテナンスのタイミングも逃しません。
モニスタは、在宅介護に求められる、新しい見守りの形です。家族の負担を軽減しながら、安心して外出できる環境づくりをサポートします。ぜひ導入をご検討ください。
まとめ:介護トラブルは事前の備えとICTの活用で乗り越えよう

介護トラブルは、家族間や介護サービス事業者との間など、さまざまな場面で起こり得る問題です。特に在宅介護では、介護者が孤立しやすく、24時間体制の見守りが難しい不安が、原因になるケースも少なくありません。
こうした課題もICTの力で解決できる時代です。見守りカメラやセンサー、情報共有ツールを活用すれば、介護の負担が減り、高齢者の安全や尊厳も守られます。家族の精神的な不安も軽減されるでしょう。
介護トラブルは、ひとりで抱え込むものではありません。ICTという新しい力を味方にして、自身と家族を守りましょう。